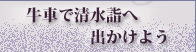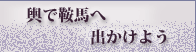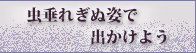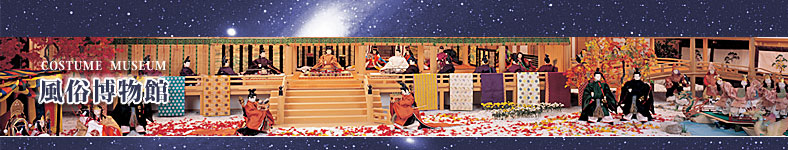
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
島原太夫晴れ姿 |

|

|
|
太夫というのは元来中国にならった官位の称号で5位相当の職で公家では殿上人であり、江戸時代でいえば大名に当たる地位で、遊芸人の敬称に用いられた。江戸時代には高級な遊女を太夫の名で呼ぶようになり、特に京都の遊廓は伝統と權威を誇っていたので太夫といえば島原ということになる。京都で「くるわ」が公認されたのは、応永年中で足利義満が許可した九条の里で、応仁の大乱後二条万里小路に移り大きな柳が2本あったので柳町といわれ、今もその跡を柳馬場といっている。公許は天正17年[1589]で更に慶長7年六条に移り、六条三筋町といわれ吉野太夫は才色兼備として今なおその名が知られている。その後、都市の発展にしたがい、都市部を離れ郊外に追われた、これが現在の島原で正しくは西新屋敷という。寛永17年[1640]この地に移転した時の騒ぎが当時の大事件であった島原の乱にも似ていたので、人々はここを島原と称したと伝えられている。 島原の太夫の装いがその頃から今のようであったわけではない。江戸時代を通じ、ますます豪華になってついに幕末を迎えた。ここではその頃を想定した。髪は京風の兵庫、前髪にはべっこうの大櫛に8本の笄、後髪には6本前後左右に前びら、櫛止め、花かんざしなど10種以上、目方はしめて3キログラム、太夫道中の時には6キログラムにも及ぶという、緋の長襦袢に白の刺繍のかけ襟、襟は折返して裏の緋をのぞかせている。中着は裾綿入りの3枚重ね。一番上の間着にはいわゆる島原褄といわれる刺繍の文様がある。これは褄から衽、胸にかけて拡がっているものをいう。次は白地、三枚目は緑地、幅広の帯を前でのし結びにしてその上から美しい打掛をかける。打掛の文様は自由であるがここでは黒地に紋づくしの文様とした。足は古式のままに素足である。道中には3枚歯の黒塗りの下駄をはく。3枚歯の下駄は文化、文政のころからのものといわれ、夏冬通じてこの姿である。戦後公娼廃止となり現在の太夫は観光客のためにその形を保持し芸妓として伝統を残している。 |

|
| 1 笄(こうがい) 2 大櫛(おおぐし) 3 前びら 4 打掛(うちかけ) 5 帯 6 中着(なかぎ) |
|
||
| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |