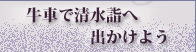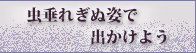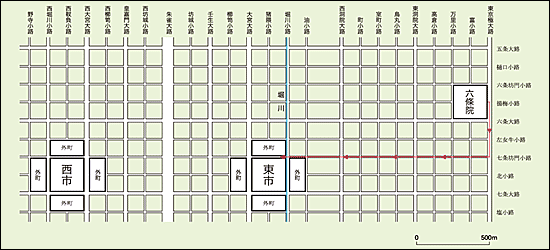|
|
|||||||||||||||||||||||
|
『源氏物語』の「夕顔」の巻に描かれた下町
『源氏物語』の話の中心は、常に身分の高い貴族階級の暮らしに限られていた。しかし中流階級の女、夕顔に想いを寄せた源氏は、仲秋の夜、五条大路に面した夕顔邸で朝を迎える。月明かりが板葺(ぶ)き屋根の夕顔邸に漏(も)れ入る光景は、寝殿造(しんでんづくり)といわれる檜皮(ひわだ)を葺いた屋根の下に住む源氏には、珍しい光景であった。隣家からは、行商(ぎょうしょう)で暮らしている人の会話や雷鳴のように地響きのする唐臼(からうす)を衝く音、またかすかに砧(きぬた)を打つ音など、源氏にとって日頃聞いたことのない庶民の生き生きとした生活音が聞こえてきた。 『枕草子』の中で清少納言は、げすの家に月の光が差し込むのももったいないといっているのに対して、『源氏物語』では源氏が、全く無縁の世界である庶民の生活風景に興味を抱いていることが対照的である。このように描かれた当時の都の庶民は、平安京の東西にある市において生計をたてていた市人(いちびと)と呼ばれている商人や職人たちである。 |
◆堀川の材木商 |
 現在の堀川通(六条通付近) 平安京には幾筋もの小さな河川が流れていたが、その中でも最も規模が大きかったのが左京の堀川と右京の西堀川であった。このふたつの川は、平安京造都以前から存在したいくつもの自然河川をつなぎ合わせて創り出された運河であった。 やや時代は降(ふ)るが、鎌倉時代に作成された『一遍上人絵伝(一遍聖絵)』には東市の東側の堀川の様子が描かれている。そこには、堀川を利用して筏を引き上げている男たちがいる。ここに見える堀川は、川幅は広いけれども水深は浅い。三人は川の中に入り、あとの二人は川辺に立って筏に繋いだ綱を力一杯に引っ張っている。堀川は、丹波からの材木を都に運ぶための重要な水路となっていた。この川は、まさに平安京の水の大動脈となっていたのである。そして、堀川の周囲にはこうした材木を扱う商人たちが集まり住むようになっていったのである。 |

◆東市(ひがしのいち)と西市(にしのいち) |
||
 現在の堀川通(六条通付近) 堀川小路を過ぎるともうそこは東市で多くの男女で賑わう界隈になった。 東市と西市とは平安京の左京と右京に左右対称形に配置されていた。しかし、市民が市で買い物をしようとしても、好きな時に好きな方の市に行くことができたわけではない。東西の市は半月交代で、月の前半は東市、後半は西市が開かれていたのである。市の内部は細かな区画に分割され、そこに小さな店舗が軒を接して並んでいた。それぞれの店は販売する商品が決まっていたから、市全体はいわば専門店街のような趣を持っていた。また、東西両市にはそれぞれ市司(いちのつかさ)という役所が置かれ、商売がうまく回っているかどうか、市の中でトラブルがないかどうかについて目を光らせていた。
しかし、平安時代が始まって間もなく、東西のふたつの市の間の関係は次第にバランスを欠いていくことになる。平安京を構成する左京と右京のふたつの部分のうち、左京は都市的発展が著しかったが、右京はそれに比べて開発が遅れていたのである。そうなるとおのずから東市の方が栄えることになり、西市はなんとなくさみしい状態になっていったのである。 こうした東西両市の明暗は、発掘調査によっても確かめられている。東市外町と西市周辺それぞれで検出された九世紀の井戸跡の埋土を分析した結果、そこには多数の植物遺体が含まれていた。東市外町の井戸には、麻、瓜、稲、桃、胡桃、栗などの栽培植物や堅果類が多量に検出される一方、道端や水田に見られる雑草類はほとんど含まれていなかった。その一方、西市周辺の井戸からは、紫蘇、茄子、瓜などの栽培植物が検出される一方、ハコベ、イヌビエといった庭や畑の植物、タデ、カヤツリグサなどの湿地・水田の植物が多量に出てきたのである。つまり、東市の一角は、樹木のほとんどない日当たりの良い空間として利用され、食品類の交易が盛んにおこなわれていたことが推定される。その一方で、西市は交易がおこなわれつつも、部分的には手入れが行き届かない、やや荒れた 状況になっていたと考えられるのである。  七条通は現在も食品関係の卸売市場に近く 食料品の店で賑う こうした状況を反映して、東市と西市との間で、扱う商品を奪い合うことなども起こっていった。承和二年(八三五)、西市司は朝廷に願い出て、錦綾(にしきあや)、絹(きぬ)、調布(ちょうふ)、綿、染物、針、櫛(くし)、油、土器(どき)、牛などの十七種の商品をおのずからの専売品とすることに成功した。つまり、これなどはすでに衰退のきざしを見せていた西市へのテコ入れ策だったということになる。しかし、それでは商品を制限された東市はおさまらない。東市司からの猛烈な反論により、五年後の承和七年(八四〇)にはこの制度は廃されてしまった。しかし、こうなると西市に勝ち目はなく、顧客を東市に奪われ、店舗には空き屋が目立つということになってしまった。承和九年(八四二)に再び西市司は朝廷に申請を出し、専売制度を復活したのである。 平安時代中期の十世紀に完成した『延喜式』を見ると、東市には五一、西市には三三の店が存在したことがわかる。米、塩、針、魚、油、櫛などはどちらの市でも買うことができたが、布、麦、木綿、木器、馬、馬具などは東市にしか取り扱っている店がない。逆に、土器、牛、綿、絹、麻、味噌などは西市の専売品となっている。紆余曲折を経て、両市の間にはこうした棲み分け関係ができていったということになる。 |
|
||
| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |