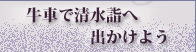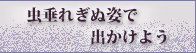|
|
||||||||||||||||||||||||
|
◆市原野(いちはらの)で輿(こし)を降りて一息)
 市原野から西を見た所 |
|
深草少将(ふかくさのしょうしょう)と小野小町(おののこまち)
謡曲「通小町(かよいこまち)」は深草少将と小野小町の恋物語として広く知られている。小町のもとに百日通うことで恋情を受け入れるという約束を結ぶが、最後の日に想い叶わず亡くなってしまう。いわゆる、百夜通(ももよい)の話である。この物語は『歌論議』の中に特定の人名をあげずに、百日通いの約束を果たせず結ばれなかった男女の話として語られているが、並の男を相手にしない絶世の美女といわれる小野小町の恋の好対象の相手として、一途な深草少将なる人物が当てられたらしい。謡曲では小野小町の化身は市原野の女として描かれ、この地の出身と考えられていたらしい。 |
|
大雲寺と「なにがし寺」
京都左京区岩倉に所在し、山号を紫雲山大雲寺と称する。本尊を十一面観音とする。『大雲寺縁起』には、藤原文範が延暦寺において、西方の峰より紫雲のたなびく様子を見いだし、開祖を義息である真覚として、園城寺の別院として創建したと記している。天元三年(九八〇)には、円融天皇の御願寺となり、朱雀天皇皇女昌子内親王の観音院建立以後、貴人の信仰を集めるようになった。また、瘧病(わらわやみ)を患った源氏が訪れた「なにがし寺」を、この大雲寺と見る説もある。なお、平安時代より現代に伝わる国宝の寺の梵鐘(ぼんしょう)は、古来の風鐸(ふうたく)を思わせる趣があり、鐘の内側に左筆で鋳造の由緒が書かれている。その格調高い左文字は、あまりにも有名である。 |
|
◆鞍馬寺大門に到着輿を降りて歩く
 鞍馬寺仁王門 しかし、ここまでは輿や牛車で来ることができたが、大門から上は歩いて登るしかない。今はケーブルカーが設置されているので楽になっているが、もちろん平安時代にそんなものがあるわけではない。美しい楓が心を慰めてくれるのがせめてもの救いで、一歩一歩石段を踏みしめながら登っていく。 |
|
◆清少納言も難儀したつづらおり
鞍馬寺の山門から少しいくと、鞍馬山の鎮守社である由岐(ゆき)神社(由岐明神)が鎮座している。ここから上がいわゆる「鞍馬の九十九折(つづらおり)」である。山上までの比高差六〇mの山腹を、くねくねとした参道が延々と続いている。清少納言の『枕草子』(第一五九段)にも、「近うて遠きもの のひとつとして「鞍馬のつづらをりといふ道」があげられている。清少納言がいつ鞍馬寺に参詣したかはさだかではないけれども、いつ果てるともない険しい山道にさしもの勝ち気な彼女も悲鳴をあげていた様子が伺え、ちょっと微笑ましくなる。 |
|
鞍馬(くらま)の火祭(ひまつり)
 毎年十月二十二日の夜に行われる鞍馬の火祭は、由岐(ゆき)神社と江戸時代後期に合祀された八所明神社の祭礼である。「さいれい、さいりょう」というかけ声とともに、次第に大きな松明(たいまつ)に火が移され、旅所(たびしょ)へと練り歩く勇壮(ゆうそう)なさまは、天慶三年(九四〇)に御所内で祀られていた神を、葦(あし)の火を焚いて遷座した故事にならっている。
毎年十月二十二日の夜に行われる鞍馬の火祭は、由岐(ゆき)神社と江戸時代後期に合祀された八所明神社の祭礼である。「さいれい、さいりょう」というかけ声とともに、次第に大きな松明(たいまつ)に火が移され、旅所(たびしょ)へと練り歩く勇壮(ゆうそう)なさまは、天慶三年(九四〇)に御所内で祀られていた神を、葦(あし)の火を焚いて遷座した故事にならっている。
由岐神社は、鞍馬寺の鎮守社で、門前の産土神(うぶすながみ)でもある。『徒然草』によると本社は疫神で、天皇の病や世間の流行病の際に、看督長(かどのおさ)の靫(ゆき)を懸けて罪人とし、平穏を祈ったという。 |
|
◆坊で休憩ののち本堂に詣る
 鞍馬寺の虎(寅の日に詣でると効験があるとされた)  本殿金堂の前の広場南端にある「翔雲台」。 中央にある板石は出土した経塚の蓋石である。 金堂の近くには、後に「転法輪堂」と呼ばれることになる丈六阿弥陀仏を本尊とする御堂が建っていた。平安時代の後期、鞍馬寺の寺運を隆盛に導いた重怡上人(じゅういしょうにん)が常の居所としていたのがこの御堂であった。上人(しょうにん)は五十三歳から亡くなる直前の六十六歳までの十三年間(大治二年〈一一二七〉?保延六年〈一一四〇〉)にわたって、くる日もくる日も念仏を唱え続け、その回数は実に十二万遍にも及んだといわれている。鞍馬寺の伽藍の前に立って耳を澄ませてみよう。どこからともなく、上人のつぶやく念仏の低い響きが聞こえてくるような気がしないであろうか。 鞍馬寺でもうひとつ重要なのは、伽藍の裏山に多数の経塚(きょうづか)が営まれていることである。経塚とは、仏法が衰退する末法の世にあって、弥勒菩薩(みろくぼさつ)が出現するはるかな未来まで正統の経典を伝えるため、金属や土器で作った容器に経を入れて土中に埋納したものである。 鞍馬寺経塚は質量ともにわが国の経塚の代表格ともいえるもので、そこの出土品のほとんどは国宝に指定されている。 |
|
僧正ヶ谷(そうじょうがだに)と義経伝説
 鞍馬寺から貴船に抜ける道では鹿に出会うことも 『平治物語』の諸本の中で最も古い形をとどめる学習院大学本では、遮那王が「僧正が谷にて、天狗・化の住(すむ)と云(いう)もおそろしげもなく、夜な夜な越て、貴布禰へ詣けり」(夜な夜な、僧正ヶ谷という天狗・化物の住むというところを恐れげもなく越えて、貴船社へと参詣した)と記されている。ところが、これが後には、遮那王が僧正ヶ谷において天狗から兵法を習ったということに、伝説が拡大していくことになる。現在の僧正ヶ谷には義経堂、義経息つぎ水、牛若丸背比べ石、兵法石、硯石など、義経関係の史跡がいくつも残されているが、これらは義経伝説の流布にともなって後世に造作されたものなのである。 |
|
||
| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |