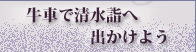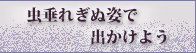|
|
|||||||||||||||||||||||
| 「藤裏葉」の六條院行幸(ろくじょういんぎょうこう)の場面では、「過ぎさせ給ふ道の興」として東の池に舟を浮かべ、「御厨子所(みずしどころ)の鵜飼」と「院の鵜飼」が鵜を使って魚を獲るところを天皇らに見せている。さらにそのあとでは、そこで獲れた鵜飼の魚と、「蔵人所(くろうどどころ)の鷹飼」が北野で狩した鳥一番(ひとつがい)を、それぞれ御階(おんきざはし)の下の左右から天皇に献上した。このいくぶん儀礼的な魚と鳥の献上は、天皇に食物を捧げることによって服属の印とする贄(にえ)の伝統を引くもので、それによって国家の秩序が満たされていることを示しているのである。太上天皇(だじょうてんのう)に准ずる位を与えられ、栄華の極みに達した光源氏を象徴する情景である。 |
◆御厨子所(みずしどころ)の鵜飼 |

鵜飼は飼い馴らした鵜に鮎(あゆ)や鮒(ふな)などの川魚を捕食させ、それを吐き出させて獲る漁法である。ふつうは鵜の首に綱をつけて遣うが、綱をつけない放(はな)ち遣(つか)いもある。また六條院行幸(ろくじょういんぎょうこう)の場面では船の上から鵜を使っているが、船を用いない徒(かち)遣いの場合もある。 鵜飼は、すでに律令制以前の日本で、天皇に貢上する贄(にえ)の漁として行われていた。その後の官制では、宮内省大膳職(だいぜんしき)に所属する雑供戸(ざつくこ)となった。平安時代になると、内膳司(ないぜんのつかさ)の御厨子所(みずしどころ)の管轄となる。御厨子所は、天皇の朝夕の御膳を調進するところである。宇治川や桂川、さらにその上流の保津川などの鵜飼は供御人(くごにん)として、御厨子所に所属して鮎などを貢進するとともに、その見返りとして京内での鮎の販売を許されていた。 |
|
桂(かつら)の供御人(くごにん)と桂女(かつらめ)
 京都の西を流れる桂川には御厨子所に所属する鵜飼(うかい)がいた。平安時代には、天皇の食膳に鮎(あゆ)を供するという意味で、供御人といわれた。そのいっぽう、京内での川魚の販売権をもっており、一家の男性が鵜飼として捕った鮎を、女性は頭に鮎を泳がせた桶を載せて、京内に売りに出たのである。その独特の風俗が後世までも愛され、「桂女(かつらめ)」とよばれている。
京都の西を流れる桂川には御厨子所に所属する鵜飼(うかい)がいた。平安時代には、天皇の食膳に鮎(あゆ)を供するという意味で、供御人といわれた。そのいっぽう、京内での川魚の販売権をもっており、一家の男性が鵜飼として捕った鮎を、女性は頭に鮎を泳がせた桶を載せて、京内に売りに出たのである。その独特の風俗が後世までも愛され、「桂女(かつらめ)」とよばれている。
桂供御人は、桂川の川魚漁だけでなくその後は水上交通も占有するようになる。平安京南部西側の祭礼である松尾祭では、桂川の西岸にある松尾大社の神輿を、船で対岸の平安京に渡す役割を担っていた。 |
◆蔵人所(くろうどどころ)の鷹飼(たかがい) |

鷹飼は、飼い馴らした鷹(たか)を野に放って鳥や小獣を捕らえさせる、いわゆる「鷹狩(たかがり)」の職掌で、古代から鵜飼と同じく天皇に貢上する贄(にえ)のための猟を行った。本来は中央アジアの遊牧民によってはじめられたもので、日本では仁徳天皇四十三年に、百済の王孫酒君が調教した鷹を百舌鳥野に遣い、雉を得たのがはじまりであるという。これにより鷹甘部(たかかいべ)を設置した。官制では兵部省(ひょうぶしょう)の主鷹司(たかつかさ)で鷹犬の調教が行われ、鷹飼に従事する鷹戸が付属した。のち鷹飼は、民部省(みんぶしょう)に移管されたりしたが、平安時代には蔵人所の管轄となって、もっぱら天皇の私的な鷹狩に従事した。 清涼殿(せいりょうでん)では、天皇が諸国から献上された鷹を見る鷹御覧(たかごらん)があり、その後親王らに鷹が下賜された。また、私的に鷹を飼うことは禁じられていて、特別な者にだけ許された。 猟場は、河内国の交野(かたの)のほか、近江国の栗太郡や伊香郡にもあったが、禁野として一般の狩猟が禁じられている。六條院行幸(ろくじょういんぎょうこう)で献じられた鳥は「北野」で狩られたとあるから、平安京北郊の北野周辺などで狩られることもあったらしい。獲物は、鶴・雁(かり)・白鳥・鴨(かも)・雉(きじ)などの鳥類や、兎(うさぎ)・狐・狸などの小獣である。 正月の大臣大饗では、鷹を手にした鷹飼が、犬を引き連れた犬飼(いぬかい)を伴って庭上に登場し、鳥を献上する慣わしがある。その装束は天皇に供奉して放鷹する狩装束で、帽子を着し、布衣と袴に腹纏(はらまき)をつけ、脚には脛巾(はばき)を巻き、腰に餌袋(えぶくろ)をつけるという独特の風俗である。 |
|
神饌(しんせん)の鳥  神社で神に供える食物と酒を神饌という。和訓では「御食(みけ)」と訓んでいる。上下賀茂社・石清水社・春日社・日吉社などの古社では、現在も古くから伝わる特殊な神饌があり、これらは古代の食事や料理の内容を伝えていると考えられている。食材そのものを供える場合もあるが(生饌(せいせん))、調理をして供える場合もある(熟饌(じゅくせん))。
神社で神に供える食物と酒を神饌という。和訓では「御食(みけ)」と訓んでいる。上下賀茂社・石清水社・春日社・日吉社などの古社では、現在も古くから伝わる特殊な神饌があり、これらは古代の食事や料理の内容を伝えていると考えられている。食材そのものを供える場合もあるが(生饌(せいせん))、調理をして供える場合もある(熟饌(じゅくせん))。
殺生(せっしょう)を禁ずる仏教の伝来によって、その後、神社の神饌も魚類や鳥獣を避ける傾向にはなったが、こうした古社では伝統的な神饌が比較的良好に保存されたと考えられる。長野県の諏訪大社では、狩猟で得た鹿や猪、兎などが供えられるのは好例であるが、畿内の神社でも、鴨や雉などの神饌を供えることはきわめて一般的である。 |
|
||
| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |