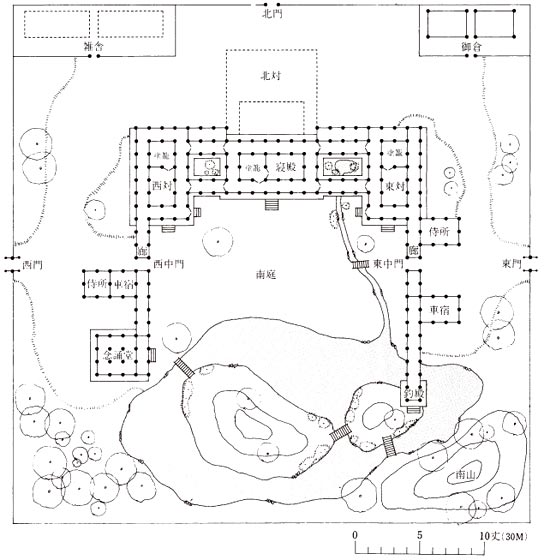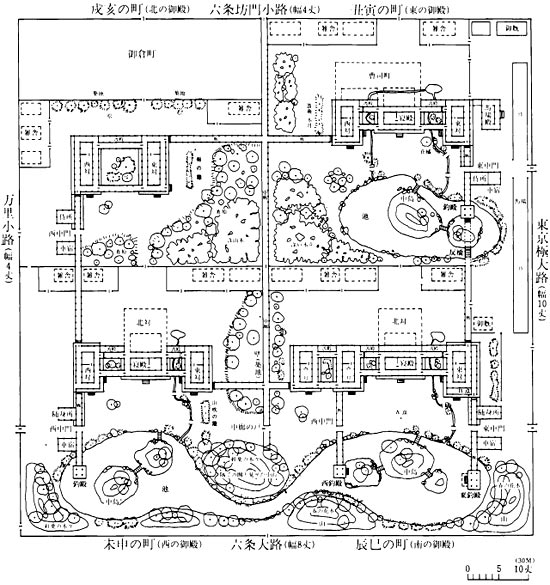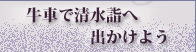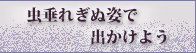|
寝殿造では、塗籠のほかは柱が立ち並ぶだけで、固定した壁がないから、殿舎の中を簾・障子・壁代(かべしろ)で仕切って生活した。障子は今日の襖(ふすま)、壁代は簾や障子に添えるいわばカーテンである。屋内をこのように間仕切りをして、さらに身辺を几帳(きちょう)・屏風・衝立(ついたて)障子・帳台で隔て、畳・茵(しとね)(座ぶとん)・地鋪(じしき)(ござの類)を敷き、厨子・二階棚(にかいだな)
・衣架(いか)・机、その他さまざまな箱などの調度を設け整える、あるいは飾りつけること、それを室礼(しつらい)とよんだ。古く塗籠を「室」といったようであるから、室礼とはその神聖な室内の調度類を礼法にしたがって整備することが原義であろう。『源氏物語』にしばしば出てくる「しつらひ」「しつらふ」という言葉はこのことを指しているが、その「薄雲(うすぐも)」の巻に、斎宮の女御(秋好む中宮)が光源氏の二条院に里下(さとさ)がりした際、寝殿の室礼を光り輝くばかりにして迎えたとある。その優美華麗なようすがしのばれる。また「蓬生(よもぎふ)」の巻に、荒れはてた末摘花(すえつむはな)の邸では、寝殿のなかだけは塵が積もっても、在るべきものをきちんと備えた室礼がしてあると書いているが、源氏は昔どおりの礼儀作法を堅く守っている姫君の貴族としての気概を大いに賞賛している。いずれにしても貴族の生活というのは、日常においても、つねに折り目正しいものであった。
当時の陰暦四月一日と十月一日は更衣(ころもがえ)であって、衣服と同じく室礼も時節に合わせて夏物、冬物と装いを改めた。「明石」の巻に「四月(うづき)にな
りぬ。衣(ころも)がへの御装束、御帳(みちょう)の帷子(かたびら)など、よし
あるさまにし出づ」とあるのはこのことで、御帳(寝台)や几帳の帷子(絹布)を冬物の練絹(ねりぎぬ)(羽二重(はぶたえ))から生絹(すずし)にかえ、畳も新調された。また室礼はいろいろな年中行事、大饗(たいきょう)・臨時客などの公儀、さらに出産・元服・裳着(もぎ)・婚礼・賀(が)の祝(いわい)・葬送・服喪といった人生儀礼に際して、その場にふさわしい装いがなされた。例えば、お産のときには、その産室は、帳台・壁代・几帳・屏風から畳の縁(へり)にいたるまで白一色にされ、産婦や側近の女房も白装束となる。『紫式部日記』は、女房の黒髪が白無垢(しろむく)の室礼に映えるさまを「墨絵のようだ」と評している。そして服喪中は、重服(ちょうぶく)(父母・夫・主人)は黒または鈍色(にびいろ)(濃いねずみ色)、軽服(きょうぶく)(妻子・兄弟姉妹)は薄鈍色に衣裳や室礼を改めるが、喪が明けて平常の色物になおされることを「服ぶく直なおし」「色直(いろなおし)」といった。重服のあとしばらく軽服に服すこともあって、この場合には、墨色の室礼がしだいに薄くなっていくわけで、そのようすも平安朝の雅(みやび)の世界であろう。『源氏物語』は登場人物の多くの死を語るなかで、この鈍色の美を描きつくしている。
寝殿造の住宅で生活する人たちは、寝殿や対のなかを東面(ひがしおもて)、西面(にしおもて)というように各自のプライベートな空間を定めて住み分けるとともに、儀式に際しては、母屋と廂を続き部屋とする放出(はなちいで)とよぶ場所を臨時に設けることによって、殿舎内を豊かに住みこなした。その際大いに役立ったのが几帳・屏風・畳などの移動可能な調度であった。ともあれ、四季の移ろい、慶弔に応じて、さま変わる色彩の豊麗さこそ寝殿造の真面目である。平安貴族はいみじくも室礼のことを装束ともいったように、住まいの装いを自身の衣裳と同じに考えていた。したがってそこには住む人の心ばえ、つまり人柄や趣味や教養といった全人格的なものが反映される。その心ばえいかんによって、住まいは上品にもなるし、卑しくもなると『源氏物語』の作者は主張している。
※この文章は平成六年京都市発行の「平安建都千二百年記念 蘇る平安京」より一部再録した。
|