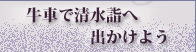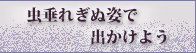|
敷地一町の上級貴族の邸宅では、寝殿は桁行(けたゆき)(東西)五間、梁間(はりま)(南北)二間の母屋(もや)を中心とし、その四周に一間の廂(ひさし)をめぐらす。
このような平面構成を「五間四面(ごけんしめん)」というが、普通梁間は二間と定まっているので省略する。一間の柱間寸法は三mぐらいである。柱は丸柱、床は板敷、廂の外側は簀子(すのこ)で、高欄(こうらん)がめぐり、南正面に五級しな(段)の階段があって、階隠(はしがくし)という庇屋根をかける。廂と簀子の境には建具が入るが、まず寝殿の東西面の南と北の端に妻戸(つまど)(両開きの枢戸(くるるど))を設けて通常の出入口とする。そのほかは格子(こうし)に簾(すだれ)をかける。南正面は儀式上の都合から一枚格子、ほかは二枚格子であったようだ。一枚格子は京都御所の紫宸殿や清涼殿のそれのように内側に吊り上げるもので、簾は格子の外にかけられる。二枚格子は社寺建築によくみられるもので、上方一枚を外側へ吊り上げ、下方は掛金(かけがね)で固定する。そして内に簾をかける。東西の対も、棟の方向が南北となるだけで、平面規模など内部の構成はほぼ同様である。これら殿舎の屋根は檜皮葺(ひわだぶき)であって、寝殿は入母屋(いりもや)造、対は切妻屋根の妻側に庇を付けた縋波風(すがるはふう)という形式であったらしい。寝殿と対の屋根構えに格差を付けたのであろう。このような優美な檜皮葺の殿舎群の俯瞰(ふかん)的景観を、当時の人びとは「三つ葉四葉の殿(との)造り」と、枝分かれした草の葉の姿にたとえている。このほか、北の築地沿いには下屋(しものや)とよぶ板葺の雑舎や瓦葺の倉などが多く建ち並んでいたようである。『枕草子』は、「雪は檜皮葺、とても美しい。雪が少し消えかかったとき、または少し降って瓦のつぎ目に雪が入った、その瓦の黒と白の取り合わせ、これもいい。時雨(しぐれ)・霰(あられ)・霜は板屋」と、自然現象のなかの屋根の異なる情趣を見事にとらえている。
さて、組入(くみいれ)(格子状の天井)のある寝殿の母屋の西または東の二間、対では北の二間は土壁で囲んだ塗籠(ぬりごめ)という部屋である。その出入口は元来は一か所であったが、のちには日常生活や儀式の都合から数か所に設けられるようになった。扉は両開きの枢戸(くるるど)である。柱だけのがらんとした空間のなかにこういう密室があったことは寝殿造の注目すべき特質といえよう。長和五年(一○一六)の京の大火で、藤原道長の京極土御門殿が焼失したことを、『栄花物語』の「玉
の村菊」の巻は記しているが、その記述に「年来(としごろ)の御伝り物ども、数知らず塗籠にて焼けぬ」とあるように、塗籠には先祖伝来の宝物が唐櫃(からびつ)や厨子(ずし)に納められて置いてあった。また、天皇の常つねの御所(ごしょ)である清涼殿の塗籠(夜御殿(よるのおとど))には、御帳台(みちょうだい)(寝台)のかたわらに剣璽案(けんじのあん)が安置してある。剣璽とはいわゆる三種の神器のうち草薙(くさなぎ)の剣(つるぎ)と八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)のことであって、天皇はこの皇位の象徴である神器と共に寝ることが任務であった。塗籠とはそういう神聖な部屋なのである。当時、貴族が寝ることを「大殿籠(おおとのごもり)」といっているが、それは本来大殿すなわち夜御殿に籠(こも)って寝ることであった。つまり、貴族は家宝に宿る祖先の霊に守護されて眠り、またその霊と交
感することによって、新しい精気を養う、という古代的な意義があったのであろう。
平安時代の人びとは物怪(もののけ)という存在を本気で信じていた。生霊(いきりょう)・死霊(しりょう)などの物怪は病人や産婦の衰弱した体にとり憑(つ)
いて苦しめ、ときには死に至らしめるものと考えられていたから、これを打ち破るための加持祈祷が盛んに行われた。この物怪を避けるために、塗籠に籠ることもあって、紫式部の仕えた中宮彰子が敦成(あつひら)親王(後一条天皇)を出産した際、その産前産後の御座所は土御門殿の寝殿の塗籠であった。また婚礼において、「衾覆
(ふすまおお)い」という夫婦の共寝する儀式が行われるのも塗籠であるし、貴族が臨終を迎える場所もまた塗籠であった。例えば『権記(ごんき)』には、一条天皇の遺骸は里内裏(さとだいり)一条院の塗籠「夜御殿(よるのおとど)」に安置されたとあるし、『讃岐典侍日記(さぬきのすけにっき)』にも、堀河天皇が清涼殿として使われた堀河院の西対の塗籠で亡くなったようすが詳しく書かれている。こうした作法はだいたい中国の儒教の教典から学んだものである。
|