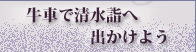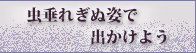代表的な襲色目(かさねいろめ)
貴族の男性が直衣(のうし)や狩衣(かりぎぬ)の合せ色を楽しみ、また高位の女性が重(かさ)ね袿(うちき)に配色の妙を競い、和様美の極致である襲色目が完成していった。平安後期に著された『満佐須計装束抄』にはそうした女房装束や狩衣の色目が、「いろいろやうやう」として詳細に記されている。
京都には昔から四季を表現する見事な色彩の世界があった。季節に咲き誇る草花や風物の配色を倣って、年中折々の行事に取り入れて雅な生活と立ち居振舞(ふるまい)が艶やかに彩られてきたのである。
しかし、その色彩についてみると、古代の人々の色彩と現代の色彩とが少し違っているのが識れる。例えば古代の緑色は、早春の新芽の黄色、春の若苗色、また初夏の若葉の萌葱(もえぎ)色、真夏の緑の葉色、さらに秋の森林の青緑に、冬の山端の濃青色と、季節を追って変化する木々や風景の色調が基本にあり、濃青緑から薄い黄緑色への複雑な色階だったのが識れる。そんな繊細な自然の色表現が襲色目に巧まれていたのであり、紅や縹はなだ、黄色も同様に複雑な色調を持っていたといえる。また襲色目では、濃色から薄色へ暈ぼかして配色をする「匂におい」や、白色まで薄くして暈ぼかし彩色をする「薄様(うすよう)」といった多様な配色手法があった。
『源氏物語』に、「かの末摘花の御料に柳の織物に よしある唐草を乱り織りたるもいとなまめきたれば」や、「桜の細長につややかなる掻かい練ねりとりそろへて ひめ君の御料なり」(明石の姫)、また「くもりなく赤き山吹(やまぶき)の花の細長は かのにしの對にたてまつれ給ふをうへは見ぬやうにておぼしあはす」(玉鬘)と綴られている。
|