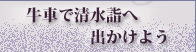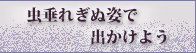|
|
||||||||||||||||||||||||
色彩と文様の雅な思想 |
| 文/藤井健三 |
|
我が国は八三八年の渡唐を最後に九世紀末には遣唐使を廃止し、政情不安となった唐との外交を絶つこととなる。その結果、平安時代は一時的に中国文化の移入が途絶えてしまった時期だったといわれ、外来文化に頼ることなく本来に立ち戻って、独自な国風文化を創り上げた時代だとされる。しかし、九世紀後半以降も朝鮮半島の新羅(しらぎ)やその後の高麗国、また渤海(ぼっかい)や遼(りょう)そして中国の民間商船を介して、唐や宋との交易が九州沿岸で活発に行われていたのが知られており、そうした民間の便を利用して中国への学僧の渡航も続けられていた。公式外交ではないが、民間力によって以前と同様に大陸文化の舶載が積極的に行われていたのである。 また仏教が伝来する飛鳥時代以前、中国の道教や儒教思想に基づく蓬莱信仰や北斗信仰、そして五行思想などが伝えられていて、そんな多様な思想を混在させて仏教を建前とした律令政権が古代に創建されていたのである。世界文化を結集した華麗な唐様式や仏教様式に支えられて花開いた奈良文化の底流に、古代中国の思想が深く根付いていたといえる。平安初期の空海や最澄によって伝えられた真言や天台密教も、印度で発した仏教が中国の思想を取り入れて再編体系化されたものであり、平安の貴族達の政務や日常の生活、庶民の拠り所であった信仰そのものも基盤が大陸の思想にあった。それらが、唐風の装いを解いて前面に現れてきたのが平安時代であった。 |
|
◆五行の色彩
|
|
古代の中国では、大陸の広大な地理的環境を包括して、全国土を治世できる理論を編み出す必要があった。そうした東南西北の地域における環境の違いを春夏秋冬の季節に置き換え、あらゆる気象条件を備えた地を揚げて、都として中央に据えた。五行思想の根本がそこにあり、大国設立を旨として南北民族の統一を図り、人の徳たる道を導く北の儒教と、神に至る術を説く南の道教との思想の習合が試みられた。 そんな空想と理想の論理が我が国にも伝えられ、実践地として満足させたのが美しい四季を持っていた京都だった。以来、権勢が京の地から離れることはあっても、四季文化を厳密に踏襲して執り行れてきた年中行事や儀式典礼をして、王城の地が京都から離れることはなかった。 このように、美しい四季の表情が政治と生活を彩り、ことごとくの物事と所作に五行思想の根本である色彩と文様が象られていった。さらに自然の道理を基とした規範が恒常化し、時代と共に様式化されて和風が完成していく。優美華麗に描かれる王朝文化と、貴族達が没頭する浄土教の華厳世界を飾る「和の雅」の色彩と文様世界に、中国古代の思想表現が明確に読みとれるといえよう。 平安の人達にとって色とはどのようなものだったろうか。五行思想では全ての物事の進化と後退の輪廻を五つの形に集約して説き、各々に黒・青・赤・黄・白の色を該当させて表している。その内容の充実を示して色彩は濃いほど貴ばれた。また紫・緑・紅・瑠黄・縹の清色と淡色を各々に従色として加え、全ての諸事の運行と表象に五色を配列してあてがった。そこに北と南の異なる環境事情を習合させて人事と政務の運用をしたのである。貴族達の位階に応じた服色や、朝廷での公私の色の別、日常における晴と褻けの色を使い分けて五行色彩の道理で綴られた。 また平安人は、こうした規律に従った色彩観念を通用させると共に、現実の微妙な自然界の色調をも物の本質として捉えて重要視した。四季・十二月・二十四節気・七十二候の微細な気候環境に呼応した多彩な色彩を観察して生活の中に採用していた。例えば、早春の草の芽生えから初夏の低木、夏の高木、そして秋の森林、冬の山端へと木々の成長と時間の経過、また人の視点を移して、黄色の苗色から萌葱、深森(みどり)、遠覆(あを)色と濃青に変化していく自然界の緑色の世界があり、これが平安時代から江戸時代までの日本の緑色の色調だった。自然の植物から得られる天然色素の色が単一色相の範囲に納まっていないのも東洋の色彩の特質である。西洋色体系の教育を受けてきた現在の私達が知らない色調の世界が存在していた。 十二世紀に記された『雅佐須計(まさすけ)装束抄』の「かりぎぬのいろいろやうやう」や「女ばうのさうぞくのいろ」に見るように、平安時代の服飾は五色の法則を基本としつつ、四季に移ろう自然の理に適った色彩の調和を模索して、雅な配色が創意されている。後世に称賛される「襲の色目」や「合せ色目」の配色が完成していた。 |
|
◆神仙と和様の文様
|
|
平安時代の文様もまた、五行思想や蓬莱、北斗信仰、そして仏教文化に大きく影響されていた。漢の武帝が蓬莱の地を東海の日本に求めて徐福を遣しめて以来、蓬莱山の具現地として我が国で種々の伝説が創作されてきた。竜宮城や浦島信仰、羽衣、高砂、翁信仰とその形を変えながら図に表して神仙の文様が語られ、東海中に支える蓬莱山の嶋が洲浜(すはま)文様に、そしてそれが松皮菱文様ともなった。天界の霊山に生える沙棠(さとう)や琅 、碧樹、絳樹、搖樹、玉樹、珠樹といった霊樹が李や竹、松、梅、藤、橘、桐の木で表され、荒海を渡る龍と天に昇る鳳凰が、亀と鶴に置き換えられて和様の形が整えられていく。それが単に島や海、波だけを描いて語られることもあり、また天地の境界線のみを記して神仙と現世を暗示して片身替り文様とされた。仏教における須弥山(しゅみせん)の表現もこの蓬莱山の基となる崑崙山(こんろんざん)から発しており、宝尽しや松竹梅、鶴亀などの吉祥文様の源がここにあった。 また、有職文様として括られる一類の文様が平安時代に形成されていった。宮中で行われる儀礼や所作の次第とその進捗状況、そして皇族や貴族の挙動を故実として記録し、後のために伝え記して儀式典礼の規範とした。有職文様はそれらに用いられた用具や衣類に付けた文様のことであり、こうした故実を詳細に纏めた有識者が後に専業となって有職故実を伝えた。 有職文様には地位や資格を表した公の文様、そして各用具に常套に用いられた様式文様などがある。また皇族や公家が用いた牛車(ぎっしゃ)の居紋や、聴しを得て各家が衣料に用いた異紋などがある。なかでも、宮中の正装だった男性の袍や女性の唐衣裳に用いられた織文は、階級のある色目に次いで皇族や公家達の出自、身分、権勢を表して重要な標識であった。有職文様の多くが牛車につけた各家の居紋から発展したといわれ、代々子孫に伝えて多様な有職文様が作られていった。桐竹鳳凰文や孔雀唐草の天皇の専用文様をはじめ、皇太子のimg鴛鴦(かにおしどり)と丁字唐草、親王の雲鶴、上皇の桐木瓜や菊木瓜、皇后の二陪(ふたえ)織物の亀甲臥蝶(ふせちょう)と小袿(こうちぎ)の花蜀江、異紋では近衛家の躑躅(つつじ)立涌、一条家や鷹司家の龍胆img(りんどうかに)唐草、中院の笹立涌、そして轡(くつわ)唐草に輪無(わなし)唐草と枚挙に限りない。 さらに有職文様の内、亀甲や七宝、輪繋ぎ、青海波、菱文、蜀江、咋鳥(さくちょう)、葵などの文様は、その発生を古代中近東近辺に辿れるのものが多く、図象の伝承経路や民族の諸問題と共に日本文化の発生を探る重要な課題としても注目されている。 しかし、武家を中心とした世に移ると、次第に為政的な内容を濃く持った儒教論理が唱えられて重きに採用されていく。それまでの五行信仰や道教的な解釈の強かった文様が、新しい儒教精神を通して君主の清廉潔白な精神や挙動に譬えて説明されていく。 |
|
||
| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |